野村兼太郎先生は、1960年6月に急逝された。現在の基準からいえば、いささか早世ではあったが、書斎で原稿用紙に向かわれながら亡くなるという学者にとって名誉ある最期であった。それから今年(2010年)はちょうど50年になる。横浜の山手教会墓地に詣で、先生の収集史料が一括して慶應義塾大学文学部古文書室に収蔵され、漸く学内で公的に収蔵場所が決まったことを墓前に報告したい。
ここで生前の野村先生を素描すれば、とにかく怖かった。とくに英国ケンブリッジ大学キングス・カレッジで学ばれた先生にしてみれば、戦後の混乱、秩序の弱体化は堪え難いことだったのだろう。大体において不機嫌で、叱られてばかりいた。褒められたという思い出はたった一回、宗門改帳の整理結果を、期限の日にご自宅に届けた時だけである。「お前はアプレだ、xxと同じだ」と叱られたり、初めてお宅へ参上した際「君の道楽は何だね」と問われたのに、うっかり「室内競技は何でもやります」と答えてしまい、一時間くらい学者はいかに時間を大切にしなければならないかを、滔々と弁じられ、眼の前のお茶に手が出せなかった。もっとも、のちに聞いたところでは、戦前には先生方とともにお宅で花札に興じられた時もあったそうである。
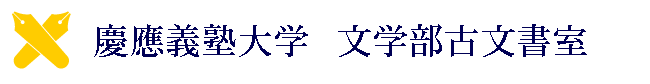

野村兼太郎先生と古文書
速水 融
一
二
野村先生が、いかに古文書、とくに戦前期には屑紙として取り扱われていた近世の農村文書に光をあて、自費で収集されたかについては『三田学会雑誌追悼号』[1]に記したとおりである。

1957年11月29日、卒業生の会にて
(野村篤氏 ご提供)
先生が、いかなる動機で古文書の収集を始められたのか、直接に知ることはできないが、文書を使った最初の論文[2]の刊行が1934年であるから、史料収集はその数年前から始められていたと考えられる。先生の個別論文は、ほとんどがご自身で収集された文書によっていた。編著の『五人組帳の研究』(有斐閣、1943年)、『村明細帳の研究』(有斐閣、1949年)でさえ大部分はそうであり、収集文書に含まれていた「五人組帳」、「村明細帳」を刊行されたのである。逆にいえば、その二種類の史料集だけで、あの大冊ができるのだから、収集文書がいかに多量であったのか想像がつくだろう。先生の文書収集には、二つのルートがあり、一つは、戦前・戦中期、近世文書がまだ史料としてほとんど利用されず、極端にいえば「紙くず」として取り扱われていたころ、三田通りの古本屋を通じて集められたものである。今はなくなってしまったその古本屋は、古紙の仕切り場へ行って、文字通り二束三文で求めた、と聞く。もう一つは、寺社、武家、商家文書で、これらは京都の古本屋から求められ、戦後も続いた。
なぜ野村先生は近世文書を収集されたのだろうか。想像をたくましくすれば、このことは先生の歴史学への姿勢、とくに英国に留学され、そこで学ばれた実証的歴史学によるのではないか、と筆者は考えている。先生は、歴史家はまず何よりも、直接には見ることのできない過去の姿を観察し、再現することから始めなければならない、という信念を持っておられた。事実の把握を抜いた歴史学上の論争には一切参加されず、研究室では、収集された文書一点一点と向き合い、丁寧に袋に入れ、表題を書き、目録を作っておられたが、その時が先生にとって最も至福の時だったかもしれない。
そういった文書への姿勢から生まれた先生の論文は、決して派手なものではなく、いわゆるグランド・セオリーに依りかかるものではなかった。取り扱う課題や範囲が何であれ、徹底した観察、そして史料批判がなされ、その限界を説かれ、史料に書かれていることが真実ではないと、何回も繰り返された。『村明細帳の研究』のような大著においてさえ、そこに収録された史料は、そのまま事実を物語るものではないことを強調されている。
しかし、先生は単なる文書の収集家ではなかった。戦争後、農地解放によって地主層が没落すると、そういう家はたいていその昔は村の庄屋だったこともあり、大量の近世地方文書が屑紙として売りに出された。そういう事態に対し、先生は「近世庶民史料調査委員会」を立ち上げられ、文部省から補助金を得て文書の保存を呼び掛け、目録作成という事業を行った。これには大勢の郷土史家も参加し、中央の史家との交流も深まる、という副産物もあった。
先生はしばしば近世地方史料は、human document である、と説いておられた。実際、近世以前と比べれば、近世地方文書は、庶民の生きざまを記す、あるいは少なくもそこから窺い知ることができるという意味で、上層特権階級の史料ではないのである。それゆえ、近世以前の文書になれ親しんできた歴史研究者からすれば、近世地方文書は、ともすれば軽んじられ勝ちであり、東京大学史料編纂所の『大日本史料』も、当初は9世紀以降明治維新までを全16編に分けて出版の予定であったが、近世初期を取り扱う第12編の一部までしか刊行されていないし、おそらくこの編ですら刊行を完了するには、今後、相当の歳月を要するとみられる。
端的にいえば、近世史料は、残存する文書の量が多すぎ、かつ全国に散らばっているので、到底一つの機関で日本全国の近世地方文書を収集することは不可能であり、所在情報を全国的に把握することさえ、膨大な予算・年月を必要とする。野村先生は、このような事態を見通され、手始めに「近世庶民史料調査委員会」を発足させ、その結果は『近世庶民史料所在目録』(全3巻、1952−1954年発行)となって刊行された。目録といっても、文書一点一点の目録ではなく、所蔵者ごとに、大約どのような近世文書があるのかを記した調査報告であったが、その後、半世紀以上を経たにもかかわらず、全国レベルでいえば、現在これを凌駕する史料所在報告書は出版されていない。
なぜ野村先生は近世文書を収集されたのだろうか。想像をたくましくすれば、このことは先生の歴史学への姿勢、とくに英国に留学され、そこで学ばれた実証的歴史学によるのではないか、と筆者は考えている。先生は、歴史家はまず何よりも、直接には見ることのできない過去の姿を観察し、再現することから始めなければならない、という信念を持っておられた。事実の把握を抜いた歴史学上の論争には一切参加されず、研究室では、収集された文書一点一点と向き合い、丁寧に袋に入れ、表題を書き、目録を作っておられたが、その時が先生にとって最も至福の時だったかもしれない。
そういった文書への姿勢から生まれた先生の論文は、決して派手なものではなく、いわゆるグランド・セオリーに依りかかるものではなかった。取り扱う課題や範囲が何であれ、徹底した観察、そして史料批判がなされ、その限界を説かれ、史料に書かれていることが真実ではないと、何回も繰り返された。『村明細帳の研究』のような大著においてさえ、そこに収録された史料は、そのまま事実を物語るものではないことを強調されている。
しかし、先生は単なる文書の収集家ではなかった。戦争後、農地解放によって地主層が没落すると、そういう家はたいていその昔は村の庄屋だったこともあり、大量の近世地方文書が屑紙として売りに出された。そういう事態に対し、先生は「近世庶民史料調査委員会」を立ち上げられ、文部省から補助金を得て文書の保存を呼び掛け、目録作成という事業を行った。これには大勢の郷土史家も参加し、中央の史家との交流も深まる、という副産物もあった。
先生はしばしば近世地方史料は、human document である、と説いておられた。実際、近世以前と比べれば、近世地方文書は、庶民の生きざまを記す、あるいは少なくもそこから窺い知ることができるという意味で、上層特権階級の史料ではないのである。それゆえ、近世以前の文書になれ親しんできた歴史研究者からすれば、近世地方文書は、ともすれば軽んじられ勝ちであり、東京大学史料編纂所の『大日本史料』も、当初は9世紀以降明治維新までを全16編に分けて出版の予定であったが、近世初期を取り扱う第12編の一部までしか刊行されていないし、おそらくこの編ですら刊行を完了するには、今後、相当の歳月を要するとみられる。
端的にいえば、近世史料は、残存する文書の量が多すぎ、かつ全国に散らばっているので、到底一つの機関で日本全国の近世地方文書を収集することは不可能であり、所在情報を全国的に把握することさえ、膨大な予算・年月を必要とする。野村先生は、このような事態を見通され、手始めに「近世庶民史料調査委員会」を発足させ、その結果は『近世庶民史料所在目録』(全3巻、1952−1954年発行)となって刊行された。目録といっても、文書一点一点の目録ではなく、所蔵者ごとに、大約どのような近世文書があるのかを記した調査報告であったが、その後、半世紀以上を経たにもかかわらず、全国レベルでいえば、現在これを凌駕する史料所在報告書は出版されていない。
三
野村先生の収集文書は、上述のように、寺社、武家、公卿、商家、農民と社会の全階層に及んでいるが、量的に多いのは、近世関東地方の農村文書である。多分、単一の古文書室で、これだけ多くの近世関東農村文書を有する機関はないことは銘記すべきである。これは、戦前期の収集が、古紙の仕切屋でなされたことからくる。もちろん中には、なぜここに、と思うような文書もある。少数ではあるが、中世の土地売券もあるし、近世中期、大隅国屋久島の検地竿次帳[3]も含まれている。残念ながら、先生がどのような経路でそれらを入手されたのかは分かっていない。
そのことは残念であるが、先生は、戦後、ご自宅のある藤沢からの混雑する列車で、三田に来られる時は必ず一箱ずつ文書を運ばれ、ご自身の研究室、われわれの研究室、図書館に置かれたことである。それらの文書は、一方で私たちが整理し、目録カードをとり、その後「関東農村の史的研究」と題して、研究結果を何回か『三田学会雑誌』に掲載した[4]。
これらの文書は、同時に、先生の持たれていた大学院の演習の教材となった。この演習は、名目は大学院の演習だったが、経済史を研究分野とする者は高村象平先生以下、西洋経済史研究者を含め全員が出席し、近世地方文書を読む会であった。筆者と共に古文書室を立ち上げた文学部の中井信彦教授も、野村先生の薫陶を受けたお一人である。野村先生は全員に文書を読ませ、読めないところを教えたり、指摘されたりした。ときどき雷が落ち、xx君は25点だ、と評価されたりした。口の悪い先輩は、「延命会」と名付けていたが、筆者は、学部卒業後2年半、アルバイト期間を含めれば3年半、常民文化研究所で全国漁村史料の調査・収集に従事してきた。文書を読むことは半ば日常的に行ってきたので、野村先生が、難しい崩し字を指差して「これなんて読む?」と問われると、読めた場合即座に答えると、もうちょっと全員が考えてから答えるように、とお叱りがあり、答えのタイミングに窮したこともあった。
先生の偉大なところは、私財をなげうって収集された文書を、私蔵とせず、没後すべて慶應義塾に贈ると決めておられたことである。このことは言うべくして易く、行うべくして難い。先生の遺志を継ぎ、贈られた二重の意味での「遺産」human document を、ただ保管するばかりでなく、新たに文学部古文書室において完了した史料の全点目録を作成し、最終的には最新の技術で古文書検索システムの完成と、文書内容のデジタル化を行い、誰でも利用できるようにするなら、これこそ慶應義塾大学の最「先端研究」となるであろう。各大学、歴史資料館などが同様の作業を行えば、不可能視されている全国の近世史料が、万人に共有されることになる。たとえ50年かかろうとも、21世紀を代表する歴史学上の達成として永遠に名を留め、野村先生からお褒めの言葉を戴けるに違いない。
そのことは残念であるが、先生は、戦後、ご自宅のある藤沢からの混雑する列車で、三田に来られる時は必ず一箱ずつ文書を運ばれ、ご自身の研究室、われわれの研究室、図書館に置かれたことである。それらの文書は、一方で私たちが整理し、目録カードをとり、その後「関東農村の史的研究」と題して、研究結果を何回か『三田学会雑誌』に掲載した[4]。
これらの文書は、同時に、先生の持たれていた大学院の演習の教材となった。この演習は、名目は大学院の演習だったが、経済史を研究分野とする者は高村象平先生以下、西洋経済史研究者を含め全員が出席し、近世地方文書を読む会であった。筆者と共に古文書室を立ち上げた文学部の中井信彦教授も、野村先生の薫陶を受けたお一人である。野村先生は全員に文書を読ませ、読めないところを教えたり、指摘されたりした。ときどき雷が落ち、xx君は25点だ、と評価されたりした。口の悪い先輩は、「延命会」と名付けていたが、筆者は、学部卒業後2年半、アルバイト期間を含めれば3年半、常民文化研究所で全国漁村史料の調査・収集に従事してきた。文書を読むことは半ば日常的に行ってきたので、野村先生が、難しい崩し字を指差して「これなんて読む?」と問われると、読めた場合即座に答えると、もうちょっと全員が考えてから答えるように、とお叱りがあり、答えのタイミングに窮したこともあった。
先生の偉大なところは、私財をなげうって収集された文書を、私蔵とせず、没後すべて慶應義塾に贈ると決めておられたことである。このことは言うべくして易く、行うべくして難い。先生の遺志を継ぎ、贈られた二重の意味での「遺産」human document を、ただ保管するばかりでなく、新たに文学部古文書室において完了した史料の全点目録を作成し、最終的には最新の技術で古文書検索システムの完成と、文書内容のデジタル化を行い、誰でも利用できるようにするなら、これこそ慶應義塾大学の最「先端研究」となるであろう。各大学、歴史資料館などが同様の作業を行えば、不可能視されている全国の近世史料が、万人に共有されることになる。たとえ50年かかろうとも、21世紀を代表する歴史学上の達成として永遠に名を留め、野村先生からお褒めの言葉を戴けるに違いない。
[1]「日本経済史学界における野村教授の業績」『三田学会雑誌』53卷10・11合併号、1960年(「野村兼太郎先生と日本経済史」として、速水『歴史学との出会い』慶應義塾大学出版会、2010年に収録)。
[2]「旗本困窮の過程について」『三田学会雑誌』28巻1号、1934年。
[3]速水「近世屋久島の人口構造―島内における家族形態の相違」徳川林政史研究所『研究紀要』昭和42年度、1968年(「第16章 近世屋久島の人口構造」として、速水『歴史人口学研究』藤原書店、2009年に収録)。
[4] 筆者による論文を一篇だけ挙げるとすれば、「都市近郊農村の諸問題―武蔵国豊島郡角筈村―」『三田学会雑誌』47巻3号、1954年、がある。
メールアドレス:keiokomonjo@gmail.com
Copyright ©, Keio University. All rights reserved.
本サイト内のすべてのコンテンツ(文章・画像など)の無断転載を禁じます。